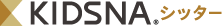ワンオペ育児とはどんな意味?ワンオペレーションに疲れたときの乗り越え方

ワンオペ育児の悩み
ワンオペ育児とはどのような状態のことをさすのかや、ワンオペ育児にまつわる悩みをママ・パパたちに聞いてみました。
ワンオペ育児とは
「ワンオペ」とは「ワンオペレーション」の略で、主にコンビニストアや飲食店で、深夜の人手が不足する時間帯に、1人の従業員がすべての仕事をこなす状況のことを意味する和製英語です。
このように、1人ですべてを行う過酷な状況に近いことから、パートナーの単身赴任や残業などの理由で、夫婦のどちらか一方に家事や育児の負担がかかっている状態を「ワンオペ育児」と呼ばれるようになりました。
一般的にママがワンオペ状態になっている家庭が多いようですが、どこからどこまでがワンオペという定義はなく、夫婦のどちらかに負担が大きくかかっているときはワンオペ育児状態といえるかもしれません。
ワンオペ育児で悩んでいること
「夫や義父母は『専業主婦なんだから母親が育児をすることが当たり前』という考えの人です。私は子育ては夫婦や家族みんなで行うことが大切だと考えているので、今の状況が続くと思うと離婚も考えてしまいます」(20代/4カ月の赤ちゃんのママ)
「嬉々としてワンオペ育児をアピールしてくる人がうざいと感じます。子育てをしているとワンオペになる時間帯はどの家庭でもあると思うので、悩み相談でない自慢のような言い方は聞いていてよい心地がしません」(30代/2歳児と3歳児のママ)
ワンオペ育児の当事者で今の生活に疲れた方や、周囲のワンオペ育児アピールがうざいと感じて交友関係に悩む方もいるようです。他には、自分の時間も作りやすい1日のタイムスケジュールが知りたいというママの声もありました。
ワンオペ育児とはどんな状態のとき?

stock.adobe.com/aijiro
ワンオペ育児になる場合、原因がいくつか考えられます。ここでは、どのようなときに、ワンオペ育児の状態になってしまうのか体験談とあわせて紹介します。
パートナーが単身赴任中
「夫が海外へ単身赴任しているため、長期休みのときにしか家にいることがありません。そのため、ほぼ1人で育児と家事に追われているワンオペ育児の日々です。子どもは2歳のイヤイヤ期で、なかなか思うように家事が進まないこともあります」(30代2歳児のママ)
パートナーの単身赴任が決まったとき、いっしょについて行ければよいのですが現実的には難しい場合もあるかもしれません。家事や育児のすべてを1人で担う場合、どうしてもワンオペレーションになってしまいます。
パートナーが仕事で帰りが遅いとき
「主人の仕事は朝が早く、帰りは子どもが寝てからの帰宅なので、どうしても日中はワンオペ育児になっています。私も仕事をしているため、仕事や育児、家事に余裕がなく、子どもに強く怒ってしまうこともあります」(40代5歳児のママ)
他にも、仕事をしていない場合でも「子どもと毎日2人きりで、家事や育児には休みがなく、ワンオペ状態に疲れた」という声も。パートナーの仕事が忙しく、家事や育児に協力してもらえないことで悩みを抱えている方もいるようです。
近くに実家など頼れる人がいない状態
「共働き家庭なので、子どもが病気になったときは、とても困ってしまいます。私たちの両親は、どちらも遠方に住んでいるので頼ることもできません。仕事が休みのときぐらいは、自分の時間を作りたいと思うこともありますが、夫は家事や育児に協力的ではなく、1人で家のことや子育てに追われています。テレビの特集でワンオペ育児の意味を知って、私はワンオペ状態なのかもしれないと思うようになりました」(30代3歳児と小学1年生のママ)
近くに両親など頼れる人がいない場合、どうしても1人ですべてを抱え込んでしまうこともあるようです。このような場合パートナーだけが頼りですが、家事や育児に協力的ではないとき、結果的にワンオペ育児になっていることもあります。
ワンオペ育児を乗り越えるコツとは

stock.adobe.com/tatsushi
ワンオペ育児の状態になってしまったとき、改善できる策はあるのかと頭を抱えてしまう方もいるかもしれません。ここでは、ワンオペ育児を「乗り越えるコツ」を紹介します。
気持ちに余裕をもつ
子どもを育てていると「ご飯はきちんと栄養バランスを考えて」「毎日掃除をするべき」など完璧に家事をこなさなければとがんばっている方も多いかもしれません。しかし、1人で、家事や育児、場合によってはここに仕事もと加わってしまうと、とてもすべてを行うことは大変です。
ワンオペ育児になっている場合には、「家事は完璧でなくても大丈夫」という気持ちの余裕が大切でしょう。子どもがケガなく元気にすごせれば、「1日がんばってできた」と自分を褒めてあげることもよいですね。
スケジュールを見直す
1日のタイムスケジュールを書き出し、育児や家事のタスクを見直してみるのもよいかもしれません。手が足りない時間帯やサポートしてほしいことを見える化すると、育児や家事の時短につながる便利家電やグッズを具体的にイメージしたり、子どもを預かってもらえる事業やサービスを活用したりしやすいでしょう。
また、ワンオペレーションの時間帯に行うことに優先度をつけ、自分のなかで「ここから先はゆとりがあるときにしよう」とボーダーラインを決められると、心が軽くなることもあります。また、スケジュールを見直すことで、パートナーにもワンオペ育児の大変さやサポートしてほしい内容を伝えやすくなるかもしれません。
パートナーと話し合いの時間を作る
ワンオペ育児の大きな原因は、どちらか一方に家事や育児の負担が大きくなっていることです。パートナーと話し合いの時間を作ることも大切でしょう。そのとき、一方的につらさや大変さを伝えても、なかなか聞き入れてもらえないこともあるかもしれません。
そのようなときには、「ご飯を作る」「ゴミ出しをする」など、家事や育児の一つひとつの動きを書き出し、パパやママそれぞれが何を行っているのかや、夫婦それぞれのスケジュールを目に見える形にしてみてはいかがでしょうか。
言葉にするより、書き出してみることで見えることもあるかもしれません。「このときが大変だから少し手伝ってもらえないかな」と伝えることで、相手も時間を作ろうと努力してくれるかもしれません。
やってもらえたときには「ありがとう」と感謝の気持ちも伝え合いましょう。ワンオペ育児が理由で離婚を考えている方は、自分の状況のつらさを冷静にパートナーに伝え、環境や関係性の修復に向けた話し合いができるとよいですね。
話を聞いてもらう

stock.adobe.com/aijiro
ワンオペ育児のときには、「どうして私だけ…」と不満が大きくなっていくこともあるかもしれません。そのようなときには、1人で抱え込まず自分の気持ちをはき出せる交流の場を作ることも必要です。
1人で悩みを抱えたままだと、気持ちも沈みがちになってしまいます。ママ友や子育て支援センターのスタッフ、ときにはSNSのなかでもよいかもしれません。愚痴や自分の思いを言える仲間がいると、スッキリして気持ちが楽になったり、またがんばろうと元気をもらえることもあるでしょう。
ベビーシッターなどの代行サービスを活用する
「ベビーシッターサービス」や「家事代行サービス」など、近年は子育てや家事をサポートする多くのサービスが充実しつつあります。
お金を払ってまで行うことでも…と躊躇してしまう方もいるかもしれませんが、ベビーシッターを利用したママのなかには「毎日忙しくワンオペ育児に疲れていたけど、思い切ってベビーシッターを活用して、子どもを預け美容院やショッピングを楽しんだらとても気持ちが楽になった」という方もいました。
自分の時間を作ることで、気分転換になったり、自分らしくいられることもあるようです。1人ですべてをやろうと意気込むのではなく、ときにはプロの力を借りて自分の時間を積極的に作ってみてもよいかもしれません。
ワンオペ育児の悩みは1人で抱えずに

stock.adobe.com/aijiro
ワンオペ育児とは、ワンオペレーションで育児を行う状態のことを指すそうです。「専業主婦なのにワンオペって何?」と、ワンオペ育児という言葉やアピールをうざいと感じる方もいる一方で、パートナーが単身赴任中など1人体制の期間が長く、ワンオペ育児に疲れたり離婚を考えたりする方もいました。夫婦だけでは手が足りないときは、育児や家事の代行サービスを活用するのもよいかもしれません。ワンオペレーションの育児に疲れを感じている方にとって、その状態を続けることが当たり前の状態にならないための前向きな話し合いができるとよいですね。
ワンオペ育児にサポート体制を作りたいときは「キズナシッター」
ワンオペ育児に疲れたとき、「パートナーの代わりに育児をサポートしてほしい」「自分の時間も作りたい」と考える方もいるようです。家族だけではワンオペ育児に対応しきれないと感じたときは、「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターにベビーシッターとして登録している方は、全員が保育士や幼稚園教諭などの国家資格保有者です。赤ちゃんや子どもだけでなく、ママやパパの気持ちに寄り添った丁寧なシッティングが好評でリピーターも増えています。
一時利用だけでなく定期利用も可能なため、パートナーの単身赴任や入院など長期的に育児のサポートを受けたいケースでも安心です。ワンオペ育児に悩んだときは、家族のサポーターとしてキズナシッターの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
お住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。